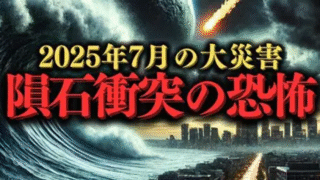現在私はエアラインでパイロットをしていますが、あこがれを持った小学生から大学生までどのようにすればパイロットになれるのかといった情報はほとんどなく(インターネットも普及しておらず情報がほとんどなかった)、たまたま知り合いにエアラインパイロットの方がいたのでその話を聞き、どうすればパイロットになれるのかを知ったという感じでした。今では、インターネットの普及により様々な情報があふれていますが、実際正しい情報かどうか判断が難しいと思います。(古い情報の可能性も多い)そのため、今回は最新の情報を皆様にお伝えし、パイロットになりたい方のための記事になればと思いブログを書きます。
エアラインパイロットになるための3つの主要ルート
日本でエアラインパイロットを目指すには、主に3つのルートがあります。それぞれの特徴を見ていきましょう。
国立のパイロット養成機関:航空大学校

航空大学校は、日本で唯一の国立パイロット養成機関として、国が設立しました。55年以上の歴史を持ち、卒業生は国内航空会社のパイロットの約40%を占めており、国内外の路線で活躍しています。
現在は独立行政法人として運営されており、宮崎(九州)・帯広(北海道)・仙台(宮城)の3つの地域にキャンパスを構え、2年間の教育課程を実施し、航空機の操縦に関する学科及び技能を教授しています。航空大学校は、国内のパイロット養成において、重要な役割を果たしています。
航空大学校で学びエアラインパイロットになるのが王道です
独自の訓練プログラム:私立大学のパイロット養成コース

近年では、私立大学でもエアラインパイロットの養成コースが増えています。東海大学は2006年に日本で初めてパイロット養成課程を開設しました。その他、桜美林大学、崇城大学、法政大学、第一工科大学、千葉科学大学などがパイロット養成に力を入れています。
これらのコースでは、座学だけでなく、実際に航空機を操縦する訓練も行われ、大学によっては海外での飛行訓練プログラムも用意されています。例えば、東海大学はアメリカのノースダコタ大学と提携し、桜美林大学はJALと連携しています。私立大学のパイロット養成コースは、多様な背景を持つ学生に、航空業界への道を開く機会を提供しています。
大学のパイロット養成コースは費用が問題なんです…
航空会社が育成する:自社養成制度

日本航空(JAL)や全日本空輸(ANA)といった主要な航空会社は、自社でパイロットを養成する制度を持っています。
これらの制度では、四年制大学を卒業した人(学部・学科は問わない場合が多い)を対象に、航空機の操縦に関する知識や技能を基礎から徹底的に教育します。
自社養成制度は、採用倍率が非常に高い狭き門として知られています。
JALグループのJ-AIRも自社養成パイロットの採用を行っており、ANAホールディングスの連結子会社であるPeach Aviationは、訓練費用の一部を訓練生が負担する「パイロットチャレンジ制度」を設けています。
航空会社の自社養成制度は、航空会社の運航基準に合致したパイロットを育成する、最も直接的なルートと言えるでしょう。
給料をもらいながら訓練ができるので費用的には自社養成が一番いいですね。ただし、かなりの倍率です。
あと、私のように自衛隊を辞めてエアラインの就職試験を受けパイロットになったり、自衛隊の割愛制度を利用してエアラインに再就職をする方法もありますが、極めて少人数の為今回は、エアラインパイロットになる方策としては適さないと思いますので、割愛します。
各ルートを徹底解説:入学条件、費用、訓練期間、取得資格
それぞれのルートについて、さらに詳しく見ていきましょう。
航空大学校

入学条件
航空大学校の操縦訓練課程の受験資格は、原則として26歳未満(当該年度の4月1日時点)であること。
学歴としては、四年制大学に2年以上在学し、62単位以上を修得していること、短期大学または高等専門学校を卒業していること、あるいは専門学校の専門課程を修了し専門士または高度専門士の称号を得ていることなどが求められます。
また、航空身体検査に合格する必要があり、矯正視力を含め両眼で1.0以上の視力が必要です。過去に航空大学校を受験し、第二次試験の身体検査B(脳波検査)で不合格となった場合は、再受験できません。
女子の入学者は例年数人と少なく、身長制限が158cm以上であることも理由の一つと考えられます。
学費
令和7年度(2025年度)の入学者の授業料は、総額で4,808,000円に値上げされました。これは、以前の3,208,000円から大幅な増額となります。授業料は、各訓練課程の開始ごとに納付する必要があります。授業料の値上げに伴い、奨学金に関するアンケートも提出が求められており、今後、貸与金額や貸与可能人数の拡大が検討される可能性があります。
訓練期間
訓練期間は、学科課程と飛行訓練課程を合わせて約2年間です。宮崎での学科課程の後、帯広、宮崎、仙台の各キャンパスで飛行訓練が行われます。令和7年度からは、帯広フライト課程が6ヶ月から5ヶ月に、宮崎フライト課程が6ヶ月から7ヶ月に変更され、宮崎学科課程の2ヶ月間はオンラインで行われる予定です。
入学時期は、以前は6月でしたが、令和7年度は翌年の2月になる予定で、入学者の希望などを考慮して、概ね3ヶ月ごとに分かれて授業が開始されます。卒業後の待機期間も短縮され、2024年時点では合計1年程度となっています。
取得資格
航空大学校を卒業すると、エアラインパイロットとして業務に必要な事業用操縦士、計器飛行証明の資格を取得できます。ただし、ジェット機などの特定の機種を操縦するための資格(型式限定)は、入社後の訓練で取得するのが一般的です。航空大学校の訓練課程は、航空業界で活躍するための基礎的なライセンス取得に重点が置かれています。
私立大学のパイロット養成コース

入学条件
私立大学のパイロット養成コースの入学条件は、大学によって異なります。
桜美林大学など一部の大学では、学生は全寮制で生活を送ります。英語能力も重視される傾向があり、英検準2級以上を入学条件とする大学もあります。
また、航空身体検査に合格することも必須条件です。東海大学の航空操縦学専攻では、理工系・文系を問わず入学が可能ですが、出願時に英語力測定試験のスコア提出が求められ、入学時には第一種航空身体検査に余裕をもって合格できる健康状態である必要があります。
学費
私立大学のパイロット養成コースの学費は、航空大学校と比較して高額になる傾向があり、4年間で2000万円程度かかると言われています。
総額で3000万円程度を見込んでおく必要があるという情報もあります。具体的な学費の例として、桜美林大学のフライト・オペレーションコースの4年間の学費は約1110万円で、別途訓練費が約1500万円必要です。
法政大学の航空操縦学専修では、4年間の学費と訓練費の合計は約2850万円に上り、寮費などを加えると約3138万円と見積もられています。
東海大学の4年間の学費は約700万円ですが、航空操縦学専攻の学生は全員に150万円の奨学金が給付されるため、実質的な学費は約550万円となります。これに加え、訓練費は約1626万円(2023年10月時点のレートで計算)です。
崇城大学の4年間の授業料は416万円ですが、入学金や実習費が別途必要です。経済的な負担を軽減するための奨学金制度も用意されており、国土交通省の無利子貸与型奨学金「未来のパイロット」は、日本航空大学校、桜美林大学、東海大学、崇城大学、千葉科学大学、新日本航空株式会社のパイロット養成課程の学生を対象に、一人あたり500万円を上限に貸与されます。
崇城大学では、独自の奨学金制度として、授業料全額または一部免除の制度があります。
訓練期間
私立大学のパイロット養成コースの訓練期間は、一般的に4年間です。多くの大学で、海外での飛行訓練が含まれており、桜美林大学では2年次秋学期から約1年間、アメリカのアリゾナ州で飛行訓練が行われます。
東海大学では、2年次から3年次にかけて約15~18ヶ月間、アメリカのノースダコタ大学に留学し、飛行訓練を行います。
崇城大学の訓練期間は、2年後期から4年までの約2年半です。
日本航空大学校には、2年制と4年制のコースがあり、2年制コースは自家用操縦士ライセンス既得者を対象として、短期間でのプロライセンス取得を目指します。
取得資格
私立大学のパイロット養成コースでは、卒業時に事業用操縦士や計器飛行証明などの資格取得を目指すことができます。
日本航空大学校では、事業用操縦士、自家用操縦士、計器飛行証明、航空無線技士、航空特殊無線技士、実用英語検定、TOEICなどが目標資格として挙げられています。
東海大学の航空操縦学専攻では、米国自家用操縦士技能証明、米国事業用操縦士技能証明(陸上単発及び多発)、米国及び日本計器飛行証明、航空英語能力証明レベル4(日本)などの取得が有利とされています。
自社養成制度
入社条件
航空会社の自社養成パイロットの応募資格は、一般的に四年制大学または大学院を卒業・修了していること(見込み含む)で、卒業後3年以内であれば応募可能な場合もあります。
学部・学科は特に指定されないことが多いです。
年齢制限は、30歳程度までとしている会社が多いです。視力に関しては、各眼の矯正視力が1.0以上であること、各眼の屈折度が-6.0~+2.0ジオプトリー内であることなど、非常に厳しい基準が設けられています。
ANAでは、書類選考の前に独自のパイロット適性検査「Flight Crew Assessment Test (FCAT)」が実施されます。
JALとJ-AIRでは、採用試験の一部が共同で行われます。
費用
自社養成制度の最大のメリットの一つは、訓練にかかる費用を航空会社が原則として負担してくれることです。
ただし、Peach Aviationの「パイロットチャレンジ制度」では、訓練費用の一部を自己負担する必要があります。
訓練期間
訓練期間は、一般的に2~3年程度です。JALの自社養成訓練プログラムは約2年半で、そのうち約5ヶ月間はアメリカのアリゾナ州で訓練が行われます。
ANAの訓練期間も約2年半で、訓練生から副操縦士、そして機長へと段階的にキャリアアップしていきます。機長になるまでには、副操縦士任命後さらに約10年かかります。
J-AIRの自社養成パイロットの基礎課程訓練は、オーストラリアのアデレードにある訓練所で行われます。
取得資格
自社養成プログラムを修了すると、採用された航空会社で副操縦士として乗務するために必要な資格を取得できます。これには、事業用操縦士免許、計器飛行証明、そして所属する航空会社の機材に応じた型式限定が含まれます。
J-AIRでは、入社要件として、オーストラリアのビザ申請に必要なIELTSのスコアと、航空無線通信士の資格取得が求められます。