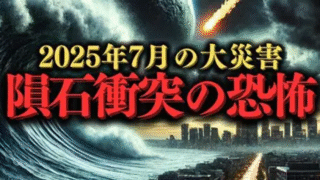はじめに
先日、高知龍馬空港に米海兵隊の最新鋭ステルス戦闘機F-35Bが緊急着陸したニュースは、多くのメディアで報じられ、関心を集めています。そして現在、この機体が3週間以上にわたって空港に留まっている状況が続いています。なぜこれほど長期間の駐機となっているのでしょうか。その背景にある事情について探ってみましょう。
予防着陸として発生した事態

今回、高知龍馬空港に着陸したのは、米海兵隊所属のF-35B戦闘機です。米軍によれば、3月25日午後に発生したこの着陸は、「飛行中に警告灯が表示されたため」の予防的な措置として行われたとのことです。これは、機体の安全性を確保するために、異常の兆候が見られた際に計画外で着陸する判断がなされたものであり、パイロットの安全を最優先した行動と言えます。幸い、パイロットは無事でした。
エマージェンシー・ランディングですね。特に単発のF35だと迅速な判断が求められますね。
長期駐機の理由として考えられること
当初の緊急着陸から3週間以上が経過しても、F-35Bは高知龍馬空港に留まっています。これに対し、地元住民からは駐機長期化への懸念や反発の声も聞かれる状況です。
なぜこれほど長期間の駐機となっているのでしょうか。最も可能性の高い理由として考えられるのは、機体の整備や修理に時間を要していることです。
F-35Bは、最新鋭のステルス技術や垂直離着陸能力を持つ非常に複雑で高度な戦闘機です。このような先進的な航空機の整備には、以下のような理由から、一般的な航空機に比べて時間と特別な手配が必要となる場合が多くあります。
- 高度な技術と専門の要員: F-35Bのシステムは非常に複雑であり、整備には高度な専門知識を持つ技術者が必要です。
- 特殊な部品: 専用の部品が必要となる場合が多く、これらを迅速に調達・輸送する必要があります。
- 機密性とセキュリティ: ステルス機であるF-35Bの整備には、機密保持や安全な環境の確保が求められます。
- ロジスティクス: 緊急着陸した場所で必要な整備を完了させるためには、遠隔地からの部品輸送や技術者の派遣など、通常の基地内での整備とは異なる手配が必要となり、調整に時間を要することが考えられます。
記事にある通り、米軍は現在、帰投に向けて機体の整備を進めているとされており、これらの要因が長期駐機につながっていると推測されます。
整備機材が整っていないところで、特に複雑な戦闘機を整備するのはすごく大変なんです。
防衛省の見解
この件について、4月18日の閣議後記者会見で、当時の防衛大臣であった中谷元氏は、駐機の詳細な理由や具体的な帰投時期について「米側との関係で詳細の回答は控えなければならない」と述べ、具体的な言及を避けました。
一方で、米軍機の日本の飛行場への出入りは日米地位協定に基づき認められていること、そして「安全な離陸が重要だ。防衛省からせかすつもりはない」との認識を示しており、安全を最優先している姿勢がうかがえます。これは、整備完了までの時間を十分に確保し、機体が万全の状態で離陸することを重視しているためと考えられます。
また、ご自身のSNSでの「命からがら空港に着陸」という表現については、「パイロットも真剣で非常に安全第一」「私なりに当時の状況を拝察し表現した」「個人の感想」であると説明されました。これも、緊急着陸という状況下でのパイロットの緊張感や安全への配慮を強調した発言と言えるでしょう。
完璧に整備して、安全に帰ってほしいですね。何よりけが人がいなくて良かったです。
まとめ
高知龍馬空港におけるF-35Bの長期駐機は、最新鋭機の緊急着陸という予期せぬ事態に対し、安全を最優先に整備を行うために必要な時間と、日米間の調整が関係している状況であると考えられます。一日も早く機体の整備が完了し、安全な形で高知龍馬空港から帰投することが望まれます。