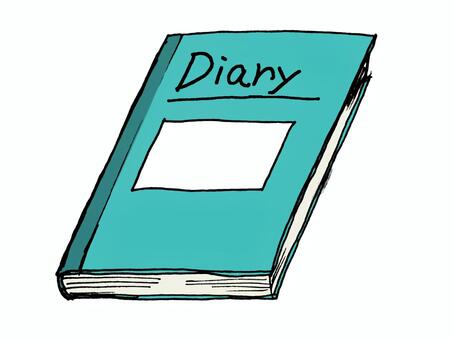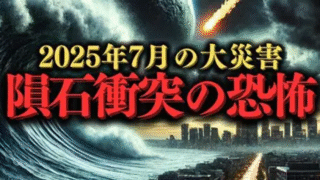はじめに
先日、済州島から金浦に向かうエアソウル便で、30代の女性客が「息苦しい」と感じ、許可なく非常ドアを開けてしまうという衝撃的な事件が発生しました。
幸い、機体は滑走路を移動中で離陸には至りませんでしたが、脱出用スライドが展開し、乗客202人を乗せた飛行機は離陸を断念せざるを得ませんでした。
この女性は航空保安法違反の疑いで現行犯逮捕されました。警察の調べに対し、彼女は閉所恐怖症があり、息苦しかったと供述しているとのことです。
この事件は、閉所恐怖症の方にとって飛行機での移動が大きな不安の種となり得ることを改めて示唆しています。
また、過去にはアシアナ航空の便でも同様の事件が発生しており、決して他人事ではありません。
そこで今回は、閉所恐怖症をお持ちの方が飛行機に乗る際に注意すべき点、航空会社のサポート体制、そしてその他の持病をお持ちの旅客が留意すべき事項について詳しく解説します。
安全で快適な空の旅のために、ぜひ参考にしてください。
時折起こってしまう事例なので皆様も注意してくださいね。
飛行機と閉所恐怖症

飛行機内という閉鎖された空間は、多くの方にとって移動手段の一つですが、閉所恐怖症の方にとっては特別な苦痛を伴う場所となり得ます。機内は座席が狭く、窓も小さいため、逃げ場のない空間に閉じ込められたような感覚を覚えやすいでしょう。
さらに、飛行中は自由に席を離れることが難しく、外部との接触も限られるため、心理的な圧迫感が増幅されることがあります。
このように、飛行機特有の環境が、閉所恐怖症の症状を引き起こしやすいと考えられます。
飛行機は狭い場所なのでなるべく大きい飛行機を選択するという手もあります🛫
閉所恐怖症の方が飛行機に乗る前の対策

- 医師への相談: 飛行前に必ず医師に相談し、自身の閉所恐怖症について伝えましょう。医師は、症状を和らげるための薬(抗不安薬など)を処方してくれる可能性があります。事前に相談することで、安心してフライトに臨むための準備を整えることができます。
- 心の準備と気分の切り替え: 飛行機に乗る前から不安を感じやすい方は、事前にリラックスできるような工夫をしましょう。例えば、瞑想や深呼吸の練習、心地よい音楽を聴く、好きな映画を見るなど、気分を落ち着かせる方法を試してみてください。また、「飛行機は安全な乗り物である」「目的地に到着したら楽しいことが待っている」など、ポジティブな思考を意識することも大切です。
- 座席の選択: 航空券を予約する際に、座席を慎重に選びましょう。通路側の席は、窓側の席や中央の席に比べて開放感があり、圧迫感を軽減できます。また、前方の席は、後方の席よりも早く降機できるため、閉鎖空間から早く抜け出したいという気持ちを和らげる効果が期待できます。非常口付近やバルクヘッドシート(前方に壁がある席)は、足元が広いため、より快適に過ごせる可能性があります。
- 航空会社への事前連絡: 予約時やチェックイン時に、閉所恐怖症であることを航空会社に伝えておきましょう。事前に伝えておくことで、座席の配慮や、フライト中のサポートを受けやすくなることがあります。
この3つの対策は凄く有効です。航空会社に自分の症状を伝えるとしっかりサポートしてくれますので躊躇しないで大丈夫ですよ☺
航空会社のサポート体制

航空会社は、障害を持つ乗客への差別を禁じる航空運送事業者のアクセスに関する法律(ACAA)に基づき、様々なサポートを提供しています。閉所恐怖症が航空機の利用に影響を与える障害と見なされる場合、航空会社は座席の配慮などの必要な便宜を提供することが求められます。具体的には、可動式のアイルアームレスト、バルクヘッドシート、足元の広い座席などが利用できる場合があります。一部の航空会社では、障害を持つ乗客に対して事前の座席指定を認めています。
エアソウルも、車椅子を利用する乗客、介助犬を同伴する乗客、視覚障害のある乗客などに対して、特別なサポートを提供しています。また、仁川空港の利用に不慣れな乗客や特別なサポートが必要な乗客のために、「MINT CAREサービス」という有料のサポートサービスも提供しています。
ただし、閉所恐怖症に対する具体的なサポートは航空会社によって異なる場合があるため、予約時に航空会社に直接問い合わせ、自身の状況を説明し、必要なサポートについて確認することが重要です。
とりあえず航空会社に言ってみましょう(^^♪
その他の持病をお持ちの旅客が注意すべき事項

- 旅行前の医師への相談: 持病のある方は、飛行前に必ず医師に相談し、航空旅行が可能かどうか、注意すべき点などを確認しましょう。時差のある場所に旅行する場合は、薬の服用時間についても医師に相談しましょう。
- 薬の準備: 服用している薬は、旅行に必要な量を十分に用意し、予備として数日分多めに持っていくと安心です。薬は、元の容器に入れたまま、処方箋のコピーや医師の診断書と一緒に携帯すると、保安検査や税関でスムーズに手続きが進むことがあります。特に、海外旅行の場合は、目的地の国で持ち込みが禁止されている薬もあるため、事前に確認が必要です。温度管理が必要な薬は、保冷バッグなどを利用して適切に保管しましょう。
- 機内での体調管理: 機内は気圧や湿度が変化しやすいため、体調管理に注意が必要です。水分をこまめに摂取し、アルコールやカフェインの過剰摂取は避けましょう。長時間同じ体勢でいると、血行が悪くなることがあるため、適度に体を動かすようにしましょう。糖尿病の方は、低血糖を防ぐために、機内食の時間を考慮して軽食を用意しておくと良いでしょう。
- 緊急時の備え: 持病によっては、緊急時の対応について事前に考えておく必要があります。例えば、アレルギー体質の方は、エピペンなどの自己注射薬を携帯し、周囲の人に使い方を説明しておくと安心です。また、自身の病状や服用している薬、緊急連絡先などを記したメモを携帯することも重要です。
空港保安検査について

空港の保安検査では、すべての乗客がスクリーニングを受ける必要があります。障害や病状により特別な配慮が必要な場合は、保安検査官に遠慮なく申し出てください。TSA Caresという、障害や病状のある旅行者をサポートするヘルプラインもあります。
薬を携帯する場合は、液体状の薬で100mlを超える場合は、保安検査の際に申告する必要があります。インスリンポンプやCPAPなどの医療機器は持ち込み可能ですが、追加の検査が必要となる場合があります。必要に応じて、TSAの通知カードを提示することもできます。
機内は閉鎖された空間なので事前の準備は大切です。
結論
飛行機での移動は、適切な準備と対策を行うことで、閉所恐怖症の方や持病のある方にとっても安全で快適なものにすることができます。今回の韓国での事件を教訓に、事前にしっかりと計画を立て、航空会社や医療機関と連携を取りながら、安心して空の旅を楽しんでください。